7月25日(火)、本会善意銀行へ播磨地方の朝日新聞販売所(ASA)でつくる兵庫県西部朝日会様より、子ども用の車イス1台を寄贈いただきました。
この車イスは、市内の小中学生や朝日新聞愛読者の協力により集めた空き缶のプルトップ、約300?などで購入されたものです。
みなさんのやさしさがこもった車イス、大切に活用させていただきます。
※写真は、ASA山崎の勝部勇治所長(写真左)から車イスを受け取る本会山崎支部長
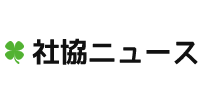
ホーム
社協ニュース

 兵庫県西部朝日会様より、車イスの寄贈! 2013/06/27
兵庫県西部朝日会様より、車イスの寄贈! 2013/06/27 7月25日(火)、本会善意銀行へ播磨地方の朝日新聞販売所(ASA)でつくる兵庫県西部朝日会様より、子ども用の車イス1台を寄贈いただきました。
この車イスは、市内の小中学生や朝日新聞愛読者の協力により集めた空き缶のプルトップ、約300?などで購入されたものです。
みなさんのやさしさがこもった車イス、大切に活用させていただきます。
※写真は、ASA山崎の勝部勇治所長(写真左)から車イスを受け取る本会山崎支部長
 福祉委員研修会・ふれあい活動連絡会のご案内(一宮支部) 2013/06/18
福祉委員研修会・ふれあい活動連絡会のご案内(一宮支部) 2013/06/18 一宮支部では、7月3日(水)午後7時から、福祉委員さんを対象に25年度の研修会を行います。今回は、「あなたの地域の見守りを考える』をテーマに、地域の見守りについて福祉委員の役割をみなさんといっしょに考えます。
また、7月9日(火)には、ふれあい活動(サロン・喫茶)の運営ボランティアのみなさんを対象に「ふれあい活動連絡会」を行います。第1回の連絡会では、平成14年9月にオープンして以来、毎月第2火曜日に開催されている「須行名ふれあい喫茶」の活動を見学し、取り組み内容や今後の活動について意見交換を行います。
詳しくは、添付のチラシをご覧ください。
 今年の「地域福祉応援事業」助成団体が決定!! 2013/06/13
今年の「地域福祉応援事業」助成団体が決定!! 2013/06/13 住民のみなさんが主体となり、地域福祉を推進する活動を支援する「地域福祉応援事業」は、平成23年度から始まり、今年度で3回目の実施となります。
4月から5月末日にかけて申請を呼びかけたところ、7つの団体からお申込みいただきました。
6月10日(月)一宮保健福祉センターで行われた「審査会」には、1団体が欠席でしたが、6団体が参加し、それぞれの取り組みについて熱く語っていただきました。
審査の結果、参加いただいた6つの団体全てに助成することを決定しました。
また、欠席された団体については、後日審査会を開催します。
なお、今回決定した助成金は、336,000円で、助成団体と内容は別紙一覧表のとおりです。
各団体の活動については、このホームページや社協広報紙、赤い羽根ニュース等で報告していきます。
※写真は「活動について説明する三方エプロンの会」です。
 一宮支部で小地域福祉活動説明会を開催 2013/06/04
一宮支部で小地域福祉活動説明会を開催 2013/06/04 一宮支部では5月30日(木)午後7時30分から、一宮保健福祉センターで「小地域福祉活動説明会」を開催しました。当日は、各自治会より自治会長と代表福祉委員に出席いただき、最初に社協段林副会長が今年度各自治会より選出された福祉委員に委嘱書を交付しました。
次に平成24年度の一宮支部での小地域福祉活動の取り組みや25年度の計画について説明した後、小地域福祉活動と福祉委員の役割について、スライドを使い説明をしました。
地域でたすけあいや支え合い活動を進めるには、自治会長や福祉委員などを中心に住民同士が力をあわせ、社協など専門機関と連携することが大切です。
自治会長、福祉委員のみなさんには、今年度も社協といっしょに地域福祉活動を進めていただきますよう、よろしくお願いします。
 休日返上で研修! がんばっています。 2013/05/26
休日返上で研修! がんばっています。 2013/05/26 「社協の介護福祉職員における価値と倫理(福祉や介護の仕事を支える「専門的な価値・倫理」)というテーマで5月26日(日)午後1時30分から本部(一宮保健福祉センター)において、介護職員の専門研修を実施し、本会のホームヘルパーや介護支援専門員、デイサービスの介護員、訪問入浴スタッフ、そして、介護予防事業担当者など50名が参加しました。今回は、講師に公立神崎総合病院のMSW(認定医療社会福祉士)の谷義幸さんをお迎えし、午後4時30分まで、休憩をとりながら約3時間、介護サービスの価値や倫理についてわかりやすい話をしていただきました。
本会の介護職員は、平日や夜間、また土曜日など業務があります。よって、全職員が集まって研修や学習を行う機会は、このように日曜日となります。休日返上で市民のみなさんのためによりよい介護サービスの提供をしようという職員の心意気をこのホームページからお伝えできればと思います。
今後とも地域の福祉の推進とよりよい介護サービス提供のため精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。(写真は、講師から話を熱心に聴く参加者)
 第6回社協チャリティゴルフ大会 参加者受付中!! 2013/05/24
第6回社協チャリティゴルフ大会 参加者受付中!! 2013/05/24毎年恒例のチャリティゴルフ大会を下記のとおり開催いたします。
集まった募金は、宍粟市の地域福祉を進める活動に活用させていただきますので、奮ってご参加くださいますようご案内いたします。
記
日 時 7月13日(土)
会 場 千草カントリークラブ
募集人員 64名
競技方法 18ホールストロークプレイ
ダブルぺリア方式(ハンディ40まで)
参 加 費 メンバー9.800円 ゲスト12.000円
申 込 み 千草カントリークラブ でんわ 0790-76-3333
 モデル地区 原自治会のとりくみ 2013/04/21
モデル地区 原自治会のとりくみ 2013/04/21宍粟市社会福祉協議会では、小地域福祉活動が住民主体で取り組まれ、継続した活動となるよう、地域の実情に合わせた活動や組織づくりを進めていくことを目標に「小地域福祉活動第1期モデル地区指定事業」を実施しています。波賀支部では、原自治会をモデル地区に指定し、連絡会議の強化や見守り活動強化を中心に、福祉活動のさらなる充実に取り組んでいます。
4月21日(日)、自治会と福祉連絡会ボランティアグループが協力し、グラウンドゴルフ大会を予定していましたが、前日の雨の影響でグラウンドゴルフは中止。そこで公民館でふれあい喫茶とビンゴゲーム大会をすることになり、総勢100名を超える人が参加しました。
ボランティアの方の愛情いっぱいの手作りおでんを味わった後は、お楽しみのビンゴゲーム大会です。会場準備は子どもたちもお手伝い。新中学1年生たちが中心となってビンゴゲームを進行しました。中学生のスムーズな進行は大人たちから「おせらしくなったなぁ」と好評でした。
参加者の声から「今は昔からの行事もだんだん減っていって、こういうことがないとみんな寄ることがないな」と、ふれあい喫茶が住民同士の安否を気遣う大切な場となっていることが伺えます。準備から片付けまで、ボランティアグループメンバーが中心となってされていましたが、わきあいあいとした雰囲気から、ボランティア同士の結束力の強さも感じられ、今後の活動がますます楽しみです。
東日本大震災から2年となるこの日、一宮ボランティア連絡協議会では、東北へみんなの思いが届くように、一宮ボランティアのつどい〜3.11東北へ届け〜を行いました。
現地へお手伝いに行くことはできないが、宍粟からみんなの思いを届けようと一宮保健福祉センターに60名が集まり、ペットボトルの灯ろうで「3.11」の文字をつくり、午後2時46分に黙とうを行いました。
黙とう後には、東日本大震災の復興支援ソング「花は咲く」を参加者で合唱し、被災地の復興をお祈りしました。
ペットボトルは、つどい開催にあたり会員のみなさまに呼びかけたところ約700本提供をいただき、3月8日に行った事前準備でボランティアのみなさんに思い思いにメッセージを書いていただきました。
ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
2月10日(日)山崎文化会館において、「第4回宍粟市地域福祉のつどい」を開催したところ、自治会長、福祉委員、民生委員、そして一般市民の方など300名の参加がありました。
オープニングでは、太子町の音楽指導者仲間グループ“セイ・マンマ”のみなさんに、NHK東日本大震災復興支援ソング「花は咲く」等を歌っていただきました。
第1部の式典では、鶴崎会長のあいさつのあと、合併後本会の理事として社協組織の基盤づくりと地域福祉活動の推進にご尽力いただいた水谷雄さんに会長から感謝状が贈られました。
第2部の基調報告では、神戸学院大学の藤井博志教授より「地域福祉は今…」と題してお話していただきました。そして本会の波多野コミュニティワーカーが、一昨年に本会が策定した第2次地域福祉推進計画(つながりふくしプラン)の内容と進捗状況について報告しました。
第3部のフォーラムでは、藤井先生にコーディネーターにお願いしました。そして地域福祉活動に取り組む3つの団体にパネリストとしてご登壇いただき、それぞれの活動について報告していただきました。
パネリストのみなさんは次のとおりです。
○西深福祉連絡会 代表福祉委員 田路伸吾さん
○NPO法人高次脳機能障害ピアサポート『ひまわりの家』
理事長 佐原美津子さん
○宍粟総合病院 病院ボランティア『めいちゃん』
清水省三さん、可藤愛子さん
つどいの最後には、まとめとして提案された「第4回宍粟市地域福祉のつどい宣言」が多数の拍手で採択されました。
今回のつどいに参加いただいたみなさん、本当にありがとうございました。
また手話通訳と要約筆記にご協力いただいた宍粟手話サークル連絡会と要約筆記ボランティア“OHPしそう”のみなさん、大変お世話になりました。
そして、市内の作業所のみなさんにも作品や写真パネルの展示等にご協力いただきました。
みなさんのご協力に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
昨年9月1日から始まった「平成24年度介護員(ホームヘルパー)養成研修事業」の全講義と実習が終了しました。
1月27日(日)一宮保健福祉センターで行われた修了式では、19名の受講生に鶴崎社協会長から修了証が交付されました。
修了式のあいさつで鶴崎会長は、「年をとり、自分が今まで築いてきた人格や生活を守ることができるのかと不安に思っている利用者に、寄り添い援助ができるヘルパーになってほしい」と受講生を激励しました。
19名の中には、この資格を取得したことで、新たに福祉施設や訪問介護事業所への就職が決まった方があります。
今後、この講座で学ばれたことを介護の現場やご家庭等で役立ててください。
みなさん、5か月間の研修、お疲れ様でした。